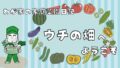人気ブログランキング

こんにちは!晴れ晴れです。
すっかり過ごしやすくなりましたね。朝はかなり寒くて、秋本番という感じですね。
今日は、秋キュウリの話題です。
この写真を見てください。どうですか?成長が遅くないですか?こんなもんなんですかね?
【左:9月23日 右:10月1日】


そこで、いつものように調べてみました。
秋キュウリの成長が止まる主な原因
秋キュウリの生育が滞る主な原因として、以下のようなポイントがあるようです。
- 気温の低下と日照時間の短縮
秋が深まるにつれて、夜間を中心に気温が下がり始めるが、キュウリの生育適温は昼間22~28℃、夜間17~18℃程度とされている。最高気温が20℃を下回り、最低気温が10℃前後まで冷え込むと、キュウリの生育スピードが鈍り、実の付き方も悪くなる。さらに秋は日照時間がどんどん短くなるため、夏ほど光合成ができず生育にブレーキがかかるようになる。つまり、温度と日照という成長エネルギーが不足して調子を崩しやすいということ。 - 根の活着不良(定植後の根付き不十分)
苗を植え付けた直後にしっかり根付かなかった場合、その後の成長が思うように進まない。乾燥に弱いキュウリは、定植直後に水分不足だと根張りが悪くなり、その後の成長が止まる原因になる。とくに秋キュウリのように、高温期に植え付けをする場合は苗が弱ってしまって活着不良を起こしやすい。植え付け日はなるべく曇りか涼しい日の午前中を選び、植え穴と苗に十分水を含ませてから植えると活着がスムーズ。定植時のちょっとした配慮が、後々の生育に大きな差を生む。 - 病害虫の被害
夏の終わりから秋にかけては、キュウリの病害虫にも油断できない時期。代表的な病気では、うどんこ病やべと病が発生しやすい。これは朝晩の気温差で露が発生し、葉が常に湿ることで病原菌が繁殖しやすくなるため。また、秋はアブラムシも発生しやすい。アブラムシは植物の汁を吸って生育を阻害し、ウイルス病を媒介することもある厄介な害虫。病害虫の被害が広がると株がどんどん弱り、成長停止どころか枯死につながることもある。 - 肥料切れ(栄養不足)
キュウリは「肥料食い」(肥料を要求する量が多い)な野菜と言われ、栄養不足になると途端に勢いがなくなる。特にプランター栽培や痩せた土壌では、一度実を付け始めると土の栄養分が早く消耗してしまう。追肥を怠ると実が曲がったり、生育が止まったりすることもある。逆に肥料過多も問題だが、基本は「少量の肥料をこまめに与える」のがキュウリ栽培のコツ。
秋特有の気候変化がキュウリ栽培に与える影響
秋ならではの気候の変化は、キュウリにプラスにもマイナスにも作用する。まず、晩夏から初秋にかけての高温多湿。今年も、9月上旬頃までは猛暑が続いたと思えば、秋雨前線の影響で大雨が降ったり。秋は天気の変動が読みづらい季節で、思わぬ長雨の後に急に秋特有の乾燥した日が続くなど、極端なコンディション変化が起こりがち。そのため、天候を常にチェックし、水やりや病害虫対策のタイミングを柔軟に調整することが求められる。
一方、秋の涼しさそのものはキュウリにとって必ずしも悪いことばかりではない。キュウリは夏野菜の中でも実は高温がやや苦手で、真夏は暑さでバテ気味になると言われる。猛暑が落ち着いた10月前後の適度な気温は、本来キュウリにとって過ごしやすいはずの環境。実際、涼しくなってから育つ秋キュウリは「実が曲がりにくく味が乗りやすい」という利点を挙げる声もあるくらい。昼間の極端な高温がなくなるため、生育そのものは安定しやすく、実の品質も良くなる傾向がある。
しかし最大の課題は日照です。春は日が長くなるにつれて成長加速するが、秋は逆に日が短くなる一方なので、栽培できる期間がどうしても短くなる。どんなに工夫しても、初霜が降りるころには栽培終了を考えなければならない。また、太陽高度が下がることで家庭菜園の環境によっては夏より日当たりが悪くなることもある。例えば庭やベランダで夏場はさんさんと日が当たっていた場所でも、秋には近隣の建物や壁の影が長く伸びて日照が減るケースがある。秋キュウリを育てる際は、できるだけ日当たりの良い場所を確保してあげることが大切。
「ウチの畑」でもできる、実践しやすい栽培管理のポイント
では、これらの秋特有の条件の中で、初心者のわたしでもできる「ウチの畑」の秋キュウリを上手に育てるための管理方法を具体的に考えてみました。
ポイントは、「夏とは違う秋仕様のひと手間」を惜しまないこと。
1. 保温対策で冷えから守る
秋後半に向けては夜温の低下が避けられないため、保温対策で冷えから苗を守ること。地温確保には黒マルチや敷き藁が有効です。ウチでは敷き藁を採用しています。植え付け時から畝に藁を敷いておけば、土が暖まり保温・保湿の効果があります。昼夜の寒暖差が激しい時期だからこそ、こうした保温の工夫で苗のストレスを減らすねらいです。


2. 水やりはメリハリをつけて
水の管理も秋仕様にシフトします。まだ暑かった9月上旬までは土の乾きも早いので毎日の水やりが必要でしたが、その後の大雨と涼しさで、今は逆に過湿に注意が必要です。基本は土の表面が乾いたら株元にたっぷり与えるやり方ですが、今は乾いていることがないほどなので、水やりは控えています。これからどんどん寒くなっていく10月は、夏ほど頻繁に水をやらなくても土がそう乾きません。「やり過ぎないこと」も水管理の大切なポイントです。晴天続きで乾燥する日は、朝の水やりに加えて葉に軽く霧吹き(葉水)するのも効果的ですが、これも朝限定です。夕方まで葉が濡れたままだと冷えと湿気で逆効果なので注意したいです。
3. 病害虫対策
ウチの畑で出やすいのは、ウリハムシです。スイカと夏キュウリをかたづけた後もしつこく飛んでいましたが、現在もこのとおりです。


ヨトウムシも見られます。見つけ次第「手でトール」していますが、すでに穴だらけの葉っぱもチラホラ。防虫スプレーで対応していますが、雨で流れることが多いのでイタチごっこ状態です。
4. 肥料は薄くこまめに
キュウリは肥料切れさせないことが大事です。しかし、秋キュウリでは「少なめの肥料を回数多く」が鉄則なんだそうです。具体的には、実がなり始めたら追肥をスタートし、以降は10日に1回程度を目安に化成肥料か有機肥料を少量ずつ株元に施すそうなんですが、ウチの場合、雌花がまだつかないので。。。
秋キュウリは心配な一方、ナスとピーマンはめっちゃ好調です。
夏より明らかにサイズアップしてます。夏は暑すぎて高温障害だったんですね。きっと。


「おおば」ちゃんは、いよいよ終わりですね。こんなになりました!花が咲きまくってます!


というわけで、今回はココまで。
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました😄次回もお楽しみに。
お帰りの際は、よろしければコレをポチッとしていただけるとうれしいです。
にほんブログ村
#家庭菜園 #秋キュウリの育て方

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ced0518.870dcde0.4ced0519.b02f9c02/?me_id=1258268&item_id=10000411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyotane%2Fcabinet%2Fimg58296581.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48de2afb.19995115.48de2afc.2b760213/?me_id=1213310&item_id=20855450&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8438%2F9784815618438_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)