人気ブログランキング

わが家の畑で順調に育っていると思っていたスイカ。
なんか最近あんまり変わってないような…。よく見てみると…


A【元気に育っているように見えるスイカの実】 B【葉っぱにズームした画像】
上の画像は、昨日の朝、わが家の大玉スイカを撮影したものです。
左の画像Aは25㎝くらいに成長した実ですが、その周りの葉っぱに異常が発生しています。
右の画像Bはその葉っぱをズームした画像です。葉っぱが、内側に巻いていて葉脈の間が黄色くなり、褐色のブツブツができています。


C【葉の先端が茶色に変色した葉っぱ】 D【青々と異常がなかった頃の葉っぱと赤ちゃんスイカ】
左のCなんかは、もはや枯れ始めています。かーなーりー、ヤバい!
ということで、今回は、緊急に原因究明と対策を講じましたので、ご報告します。
みなさんのスイカが元気に育つように、ぜひ参考にしてみてください!
ヤバい症状と原因と基本的な対策
わが家のスイカに見られるものをアンダーバーで示しました。
症状1. 葉が黄色くなっている
全体的に黄色い場合
- 原因: 窒素不足の可能性が高いらしい。窒素は葉の成長に不可欠な栄養素。不足すると、古い葉から養分が新しい葉に移行するため、下葉から黄色くなる。
- 対策: 即効性のある液体肥料(窒素成分が多いもの)を施すか、追肥として化成肥料を与える。
葉脈だけが緑で、葉脈の間が黄色い場合
- 原因: マグネシウムや鉄などの微量要素が欠乏。特にマグネシウムは光合成に必要な成分。
- 対策: マグネシウム欠乏であれば苦土石灰や硫酸マグネシウムを、鉄欠乏であればキレート鉄?などの微量要素肥料を与える。
新葉が黄色い場合
- 原因: 鉄欠乏や、土壌のpHが高すぎる(アルカリ性すぎる)ために栄養吸収が阻害されている可能性がある。
- 対策: 土壌のpHを測定し、必要であれば調整します。鉄欠乏の場合は、微量要素肥料を与える。
症状2. 葉に斑点や病変が見られる
黒い斑点やカビのようなもの
- 原因: 炭疽病、べと病などの真菌性疾患。湿度が高く、風通しが悪い環境で発生しやすい。
- 対策: 病気に強い品種を選ぶ、株間を十分に開けて風通しを良くする、マルチングで土壌からの跳ね返りを防ぐなどが有効。発生してしまった場合は、適用のある殺菌剤を散布することも検討。
白い粉のようなもの

【中央の葉脈付近が白い葉っぱ】
- 原因: うどんこ病。葉の表面に白い粉状のカビが発生。光合成が阻害され、生育が悪くなる。
- 対策: 初期であれば重曹水などを散布するのも効果的。ひどい場合は、うどんこ病に効果のある殺菌剤を使用。
症状3. 葉がしおれている、または萎縮している

【暑い日中、しおれてしまったスイカの葉っぱ】
日中にしおれて、夕方には戻る場合
- 原因: 水不足。特に暑い日中は、蒸散量が多いため一時的にしおれることがある。
- 対策: 朝の早い時間にたっぷりと水を与えよう。土の表面が乾いたら水やりのタイミング。
常にしおれている、または株全体が萎縮している
- 原因: 根腐れ(水のやりすぎ)や、つる割病などの土壌病害。根が傷つくと水分や養分を吸収できなくなる。
- 対策: 水のやりすぎに注意し、水はけの良い土壌で育てることが重要。つる割病は一度発生すると厄介なため、発病株は抜き取り、連作を避けるなどの対策が必要。
葉が縮れていたり、奇形になっている
- 原因: ウイルス病、または吸汁性害虫(アブラムシ、ハダニなど)による被害。ウイルス病は治療が難しく、害虫が媒介することもある。
- 対策: 早期に害虫を駆除することが重要。ウイルス病が疑われる株は、他の株への感染を防ぐためにも早めに処分しよう。
症状4. 葉に穴が開いている、食害がある
- 原因: 病気ではなく、害虫による食害です。ウリハムシ、アオムシ、ヨトウムシなどが葉を食べてしまいます。
- 対策: 早期発見・早期駆除が大切。見つけたら捕殺したり、防虫ネットをかけるなどの物理的な対策が有効。ひどい場合は、適用のある殺虫剤の使用も検討する。
症状5. 葉の縁が茶色くなる、枯れる
- 原因: カリウム不足や、乾燥による生理障害。
- 対策: カリウムは果実の肥大に重要な栄養素。追肥でカリウムを含む肥料を与えたり、水やりを適切に。
まとめ 収穫まであとわずか!わが家で実際にやった対策はコレ!
わが家で「肥大期」に入ったスイカ!
この時期の管理が、甘くて大きなスイカを収穫できるかどうかの分かれ道!
今回わたしがやった対策は、次の3つです!
対策1. 水やりが基本!乾燥は大敵…らしい
スイカの実の約90%は水分。そのため、肥大期には十分な水やりが何よりも重要。肥大期に乾燥させると、実の肥大が止まってしまったり、果肉が硬くなる原因になります。
改善点
- 植え付けから続けてきた乾燥を防ぐはずの黒マルチ。思い切ってはずして、株元のまわりをスッキリさせてみました。まいた水が株元の10㎝ほどのエリアしかかかっていなくて、黒マルチが逆に日中の暑さで高温になっていました。とりあえず、これで様子を見ます…。。。
対策2. 追肥で栄養補給!窒素・リン酸・カリウム・マグネシウムのバランスを重視
実を大きくするためには、たくさんの栄養が必要。葉っぱの色が教えてくれたSOS!
しかし、追肥って、葉っぱから吸収させることもできるんですね~。知らなかった…。
- 肥料の種類: スイカの肥大期には、特にリン酸とカリウムが重要。リン酸は実の成長を促し、カリウムは糖度を高め、果実の品質を向上させる。窒素も必要ですが、与えすぎるとつるばかり茂って実が大きくならない「つるぼけ」の原因になるので注意が必要。
- 追肥のタイミングと量: 1つ目の実が握りこぶし大になった頃から追肥を始め、2〜3週間に1回程度与えよう。株元から少し離れた場所に溝を掘って肥料を埋めるか、液肥を与えるのが効果的。
今回は、コレ↓を薄めて使ってみました!マグネシウムも入っているのでいいかも!

対策3. 玉直しと敷きワラで「色ムラ」と「病気」を防ぐ
スイカは地面に接している部分が黄色くなりやすく、また病害虫の被害を受けやすい。これを防ぐためには玉直しと敷きワラが有効。
- 玉直し: 実が成長してきたら、数日に一度、そっと実の向きを変えてあげます。こうすることで、太陽の光が全体に当たり、均一に色づき、甘みも均等に。ただし、まだ小さい実や、へたの部分が弱い場合は無理に動かさないようにして注意。
- 敷きワラ(座布団): 実の下にワラや古い新聞紙などを敷くことで、地面からの熱や湿気を遮断して、病害虫(特にウリハムシやダンゴムシなど)の侵入を防ぐ。また、土の跳ね返りによる病気(炭疽病など)の予防にもなる。


【硬いレジャーシートの上から、やわらかい“座布団”を敷いてあげました】
収穫まであとわずか。
水やり、追肥、そして日々の観察と適切な管理が成功の鍵を握ります。大きくなっていく実ばかりに気を取られてしまわないように、葉っぱや株元など、実を育てている大事なところの変化に注意して、甘くて大きなスイカを見てみたいものですね。
みなさんも、ぜひこの記事を参考に、自慢のスイカを収穫してくださいね!
ということで、今回は、この辺で。。。
お帰りの際は、よろしければコレをポチッとしていただけるとうれしいです。
にほんブログ村
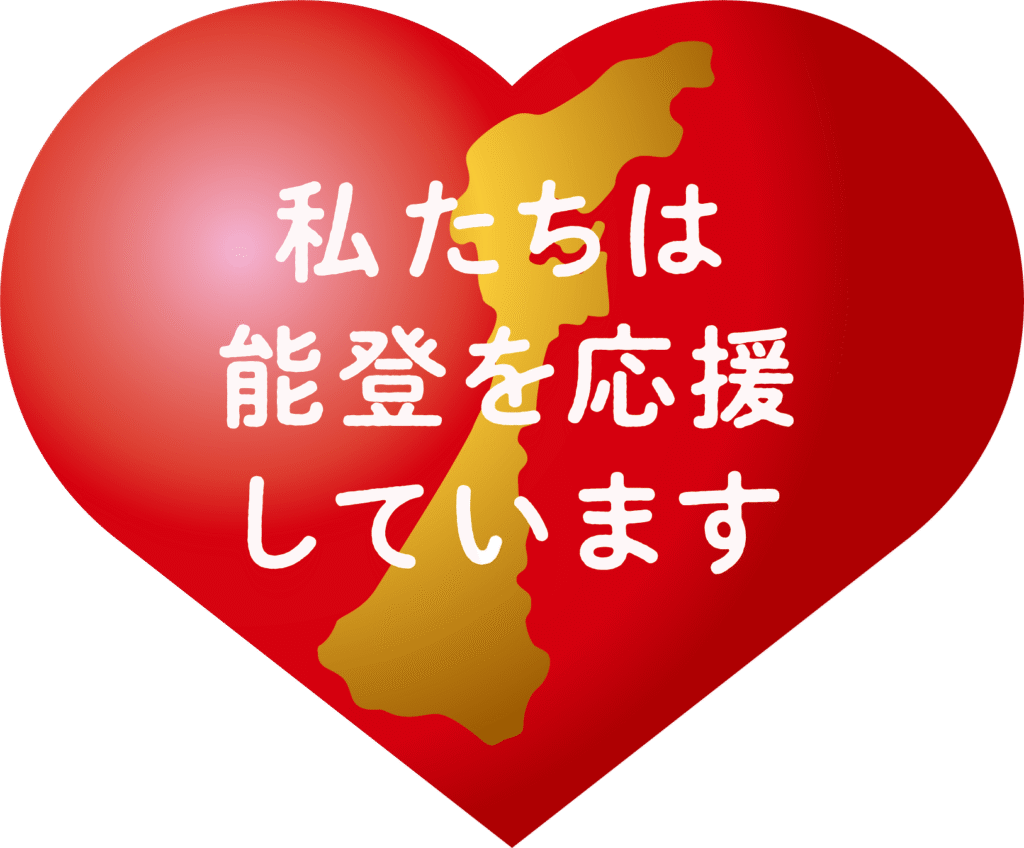
金沢の美味しい押し寿司です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a471874.e5e3e900.4a471875.e736e931/?me_id=1296421&item_id=10002835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanazawa-honpo%2Fcabinet%2Ftamazushi%2Ftamazushi04-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a471c5a.28ef2c28.4a471c5b.cf44149a/?me_id=1322025&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanazawa-tamazushi%2Fcabinet%2Fsushi01%2F01001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

