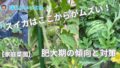人気ブログランキング

家庭菜園で人気の野菜、ピーマン。「育てやすい」と聞いて挑戦したものの、「あれ?なんかうまくいかない…」と首をかしげた経験はありませんか? 私もその一人です。今回は、現在進行形の私のピーマン栽培での苦労と、そこから学ぶ「ピーマン栽培は実は奥深い!」という真実をお伝えしたいと思います。
初めてのピーマン栽培、順調なスタートからの暗転
本格的に家庭菜園をやろうと、この春、妻といっしょにホームセンターへ。ホームセンターで元気なピーマンの苗を見つけ、「これいいんじゃない?」と買ってみたピーマンの苗。植えた最初のうちは、青々とした葉を茂らせ、かわいらしい花を咲かせるピーマンの成長に「おー。やっぱ、いいじゃん」と心を躍らせていました。
しかし、ある日を境に異変が…。

【落ちたピーマンの実】
【私がぶつかっている壁】
- 落花・落果の多発: 葉っぱも旺盛で、花もたくさん咲くのに、実が大きくならずに落ちてしまう。
- 実の変形:最初の実はピーマンらしい形・大きさでしたが、だんだんイビツな形で小さくなっていきました。
まるでピーマンに「助けて!」と言われているかのようです。そこで、私は、ネットで「ピーマン 育て方」「ピーマン 落花」などと検索しまくり、現在は試行錯誤の真っ最中。なかなか改善しないので、ちょっと凹んでいます。
要点チェック!ピーマン栽培の「本当の難しさ」はここにある!
これらの経験を通して、私が痛感したのは、ピーマン栽培の「本当の難しさ」です。
1. 繊細な環境への要求
ピーマンは高温多湿を好む一方で、水のやりすぎや乾燥、急激な温度変化にも敏感。少しの環境変化で、すぐに生育に影響が出てしまうらしい。
→ すぐそばのミニトマトに気を取られて、水不足だったかも…
2. 肥料管理の難しさ
ピーマンは肥料を好む野菜ですが、与えすぎると茎ばかり伸びてしまったり(徒長)、逆に少なすぎると実つきが悪くなったりと、適量を見極めるのが非常に難しい。
→ 追肥したのが最近で、初めが好調だっただけに放置してしまっていたかも…
3. 病害虫の標的になりやすい
アブラムシやハダニ、うどんこ病など、ピーマンを狙う病害虫は多岐にわたり、少しでも対策を怠るとあっという間に広がってしまう。
→ これは、大丈夫。今朝見ても、病害虫は発生していない模様。
4. 連作障害のリスク
同じ場所でピーマンを育て続けると、土壌の栄養バランスが偏ったり、病原菌が増えたりして、生育が悪くなることがある。
→ いちばん可能性が高いのがコレ。去年も義母がナスとピーマンを植えてた。
ピーマン栽培の隠れた重要ポイント:整枝の必要性
私がピーマン栽培で苦戦している原因の一つに、「整枝」の重要性をわかっていないということがあります。整枝とは、植物の枝を剪定したり、誘引したりして、株の形を整え、適切な成長を促す作業のこと。これを怠ると、せっかくのピーマンがうまく育たない原因になってしまうのですが、これがまぁむずかしい。
整枝をしないとどうなる?
- 風通しが悪くなる: 葉や枝が茂りすぎて株の内側が密になり、病気や害虫が発生しやすくなる。
- 日当たりが悪くなる: 葉が重なり合って光が十分に当たらなくなり、光合成が効率よく行われず、実のつきが悪くなったり、成長が遅れたりする。
- 養分が分散される: 必要以上に枝葉が茂ることで、植物が吸収した養分が実ではなく枝葉の成長にばかり使われてしまい、実が大きくならなかったり、収穫量が減ったりする。
- 実の品質が落ちる: 日当たりや風通しが悪くなることで、実の色づきが悪くなったり、味が落ちたりすることがある。
ピーマンの主な整枝方法
ピーマンの整枝にはいくつか方法がありますが、家庭菜園で一般的なのは「3本仕立て」や「4本仕立て」と呼ばれる方法です。
- 主枝の選定: 苗が育ってくると、最初の花のすぐ下から力強い脇芽が2~3本出てくる。これらを主枝として残し、それ以外の脇芽は取り除く。
- わき芽かき: 主枝以外に出てくるわき芽は、基本的に小さいうちに取り除く。特に、主枝の股から出るわき芽は放置するとどんどん大きくなるので、こまめに取り除く。
- 下葉かき: 収穫が進み、実がついていた下の方の葉や、黄色くなった葉は、株の風通しを良くするために取り除く。
実がなり出してからの整枝のポイント
二股になっている枝の太い方を残して、細い方を切ると良いそうです。下の画像は、その原則で整枝したものです。


横から見た様子 【整枝前】葉っぱがゴチャゴチャしてます 【整枝後】 スッキリしましたね。


上から見た様子 【整枝前】葉っぱが重なり合っています 【整枝後】 重なりが少なくなっています。
整枝のタイミングと注意点
- タイミング: わき芽が小さいうちに行うのが理想的です。大きくなってからだと、株に負担がかかるので注意。
- 切り方: ハサミや手で丁寧に、付け根から切り取る。病気の原因になるので、ちぎるように無理やり取るのは避ける。
- やりすぎに注意: 整枝しすぎると、光合成を行う葉が減ってしまい、かえって生育が悪くなることがある。株全体のバランスを見ながら行おう。
適切な整枝を行うことで、ピーマンは元気に育ち、美味しい実をたくさんつけてくれるはずなんですが。。。ぜひ挑戦してみてください。
ピーマン栽培のコツは「観察力」と「あきらめない心」
私の失敗談ばかりお話ししましたが、決してピーマン栽培が不可能だと言いたいわけではありません。これらの経験から、私はピーマン栽培において最も大切なのは「ピーマンの声に耳を傾けること」、つまり「細やかな観察力」だと学びました。

[参考:元気なピーマン]
- 葉の色はどうか?
- 花のつき方はどうか?
- 実のつき方はどうか?
- 虫はついていないか?
毎日、ピーマンの状態を注意深く観察し、異変に気づいたらすぐに適切な対策を講じる。これがピーマン栽培成功への第一歩です。そして、何よりも「あきらめない心」。時にはうまくいかなくても、そこから学び、次に活かすことが大切なんです。
今年は、まだまだ試行錯誤が続けます。いまの私と同じように「ピーマン栽培、難しい…」と感じている方も、きっと大丈夫です。ピーマンとの格闘を通して、早くあなただけの栽培ノウハウを見つけて、ぜひ美味しいピーマンを収穫してくださいね!
もし、新しくわかったことがあったら、コメントしていただけるとうれしいです。試せることは、さっそく試してみたいと思います。
ということで、今回は、この辺で。。。
お帰りの際は、よろしければコレをポチッとしていただけるとうれしいです。
にほんブログ村
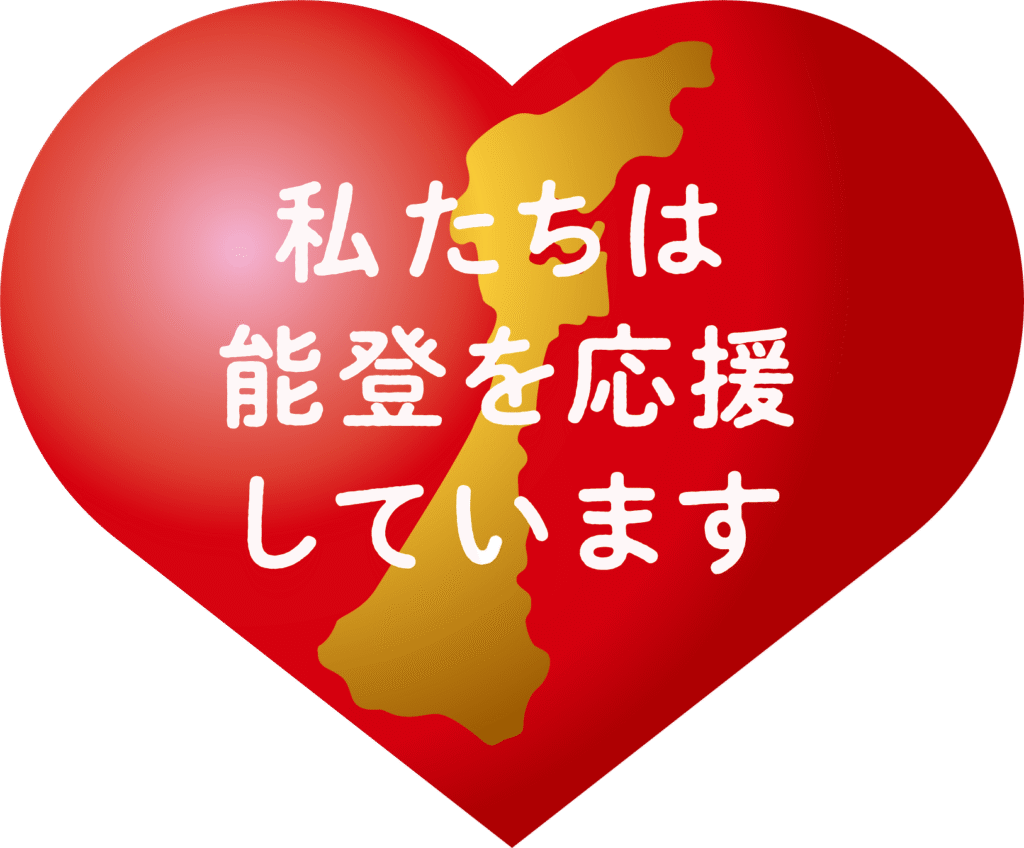
金沢の美味しい押し寿司です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a471874.e5e3e900.4a471875.e736e931/?me_id=1296421&item_id=10002835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanazawa-honpo%2Fcabinet%2Ftamazushi%2Ftamazushi04-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a471c5a.28ef2c28.4a471c5b.cf44149a/?me_id=1322025&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanazawa-tamazushi%2Fcabinet%2Fsushi01%2F01001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)